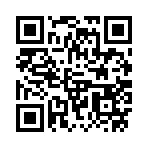古語の厳密な現代語訳は可能なのだろうか
あくまで私のこれまでの感想に過ぎないが、果たして古語を厳密に現代語へと訳すことは可能なのだろうかと疑問に思うことがしばしばあった。そして、古語について多少のことを調べた挙げ句に出た結論は、おそらく厳密には不可能なのだろうということである。だから、今ではその様な立場に立つこととしている。あくまで個人的にはということではあるが。不可能だろうと思う理由は、古語には現代語には存在しない言葉が存在することである。どういうことかというと、ある古語は多少形を変えながら現代語にも残っているが、別のある古語はそうはならなかったということである。そうはならなかった古語はどうなったかというと、消えてなくなったということである。その古語は現代語においては文字通り跡形もなくなってしまっている。
現代まで生き延びたが・・・
現代まで生き延びた言葉として一つ例を挙げると、助動詞の「た(だ)」(以下では単に「た」とする)がある。「歩いた」、「食べた」、「読んだ」の「た」のことだ。この「た」は古語では助動詞の「たり」であった。古語の助動詞「たり」は一説には助動詞の「つ」までさかのぼることができるというから、その説によるならば、助動詞「つ」もまた変形しながら、現代まで生き延びてこられたと言える。
助動詞「つ」 →(変形)→ 助詞「て」(ただし、他の説あり)
助詞「て」+動詞「あり」 →(変形)→ 助動詞「たり」
助動詞「たり」 →(変形)→ 助動詞「た」
これら古語の「つ」や「たり」は完了の意味を持つことから、それらが変形してできた現代語の「た」も完了の意味を持つこととなる。現代人もそのつもりで特に何らの抵抗感もなく「た」という言葉を完了の意味で用いることとなる。もちろん、辞書や文法書を引いてみると「た」には完了の意味が紹介されている。しかし、中にはこう思う人がいるかも知れない。(あれ、助動詞の「た」っていうのは過去の意味を表す助動詞じゃなかったの)と。そうですねぇ、確かに辞書や文法書を引くと「た」には過去の意味も紹介されています。つまり、現代語の「た」には過去の意味もあるし、完了の意味もあるし、ということになっています。
だが、ここで現代語の場合にはちょっとした混乱や誤解が生じるのかも知れない。なぜなら、ある人が「山に登った」と言ったときにその人は「た」を完了の意味で使ったのか、過去の意味で使ったのか明確に区別する方法がないからだ。そんなことはどちらでもいいじゃないかと言われればそれまでだが。過去に起きた出来事はすでに完了しているわけだし、過去も完了も同じようなものだと言われそうである。というか、むしろ、「た」は完了というよりも過去の助動詞だと多くの人に思われている可能性は大きい。なぜなら、辞書を引くと、「た」の意味として一番目に「過去」と紹介し、二番目に「完了」と紹介しているものが多いことに気付くからである。手元にある複数の辞書を調べと、一番目に「過去」とし、二番目に「完了」としているものは5つ。一番目に「完了」とし、二番目に「過去」としているものは1つ。明確に示しておらずどちらとも言えないものが2つという結果になった。また、中学生用の国文法の参考書を一冊見てみると、これも一番目「過去」、二番目「完了」というものであった。世の中のすべての辞書や参考書を調べたわけではないが、もはや「た」という助動詞は多くの人が多くの場合に過去の意味で使っているのだろうなぁということが推測される。
完了の助動詞「たり」 →(変形)→ 完了の助動詞「た」
完了の助動詞「た」 → 完了と過去の助動詞「た」
完了と過去の助動詞「た」 → 過去と完了の助動詞「た」
過去と完了の助動詞「た」 → 過去の助動詞「た」
では、「た」という助動詞は多くの人が多くの場合に過去の意味で使っているのだということを前提にしてみると、その人々が完了の意味を言葉で表現しようとした場合、どのような言葉が用いられるであろうか。おそらく、「てしまう」やそれがくだけた形の「ちゃう」とか「ちまう」という言葉なのだろう。「てしまう」は例えば「食べてしまう」とか「書いてしまう」という使われ方をする。
過去の助動詞「た」との認識→「完了」を意味する「てしまう」の発生?
この「てしまう」は、助詞「て」+動詞「しまう」でできている。実はこの助詞「て」は先ほど上のところでお示しした助詞「て」なのである。この「て」は一説には古語の完了の助動詞「つ」が変形してできたものであるということであった。つまり、この助詞「て」自体が潜在的には完了の意味を持っているということが言える。そして、更にその後ろに「しまう(終う、了う)」と一言付け加えて更に加えて完了の意味を表現していると言えるのである。このように掘り下げてみるならば、「てしまう」は屋上屋を架した構造の言葉になっていると言えなくもない。それなのに「てしまう」を縮めて「ちゃう」や「ちまう」という表現まで存在する。「てしまう」に伸ばしてから「ちゃう」や「ちまう」に縮める。このことはわざわざ手の込んだことをしているように見える。しかし、そんなことをしなくても縮めたいのであれば、初めから縮まっていたのである。それは本来の意味としての完了の意味を持つ単なる助動詞「た」なのである。由緒を辿ると助動詞「た」こそが完了の意味を表す助動詞なんだと言える。あくまで言葉の由緒ということを重視した場合の話ではあるが。だが、言葉は時とともに変遷するものであるのは洋の東西問わずこれまで起きてきたことであるから、「てしまう」や「ちゃう」や「ちまう」という表現を批判するつもりはない。このようなことを書いている私もそんな表現を使うことはある。しかし、助動詞「た」は本来完了の意味を表すものであり、そのつもりでその言葉を使おうと普段から意識するようにはしている。が、それは個人的な志向である。なぜその様な意識を持とうとするかというと、それは由緒に基づいた言葉の使い方であり、従って原義を押さえているということでもあり、更にこの上なく単純だからである。「た」、すなわち「完了」こそがこれ以上縮めようのない単純かつ明快な認識だと思えるからである。
単純にこの点を抑えておけば少々のことでは助動詞「た」に接したときに混乱することはない。例えば「昨日、山に登った」と聞いたときそれを話した人は過去の意味のつもりで助動詞「た」を使っているのかも知れないが、聞いた側としては完了の意味の「た」だと思っておいて問題はない。昨日山に登ったのは過去のことではあるが、完了していることでもあるからだ。この場合、過去と完了の間に意味的には大きなズレは存在しない。しかし、「明日、山に登ったとして・・・」という会話の場合はどうであろうか。「昨日、山に登った」の「た」を過去の意味で話していた相手も今回ばかりは「明日、山に登ったとして・・・」の「た」を過去の「た」とは思っていないはずなのである。聞いた側としては「た」、すなわち「完了」と頭の中にあれば、この場合の「た」も「完了」なのだと認識できるのだから単純な話で終わる。完了は完了でも未来における完了である。しかし、聞いた側が仮に「た」、すなわち「過去」と思っていたのならば、ちょっとした頭の中の混乱が生じるかも知れないし、そうでなくてもこの場合の「た」は「過去」ではなく「完了」なのだなと場合分けをしなければならなくなる。つまり、ほんの一瞬かも知れないが認識がワンテンポ遅れる恐れがある。
過去の助動詞「た」と認識→「明日、山に登ったとして・・・」への対応は困難
完了の助動詞「た」と認識→「明日、山に登ったとして・・・」への対応は無難に可能
このように「過去」と「未来」の両方に対応できるという点でも「た」、すなわち「完了」と押さえていることの方が安全であるといえる。逆にいえば、「た」、すなわち「過去」と捉えていることは危険なことだといえなくはない。本来、「完了」と「過去」とは全く意味の違うものである。現在から見れば完了した物事は過去のものなんだといえるが、それはあくまでも基点を現在に置いた場合に限った話である。しかし、実際に「完了」は現在だけではなく、未来にも過去にも起こりうる。「完了」とは「完全に終わる、終える」ということであって、「終わる」のは現在に限ったことではなく、未来にも起こりうるし、過去にだって何度も起きてきた。だから、「完了」と「過去」は似たようなものなどではなく、全くの別物だとして理解しておくことが安全なのである。さもないと自ら無用な混乱を招きかねない。ここで言う混乱とは認識不足や誤解のことである。
消えた「過去」
もし、現代語を使う中で、先ほど述べた理由から助動詞「た」、すなわち「完了」との認識に限定することにしたとしよう。その場合、過去を言い表す表現が見当たらなくなってしまう。現代語ではこのように行き詰まってしまうのだから、やはり「た」に過去の意味を持たせようかということになってしまう。日本語に現代語しか存在しないのならそうせざるを得ない。しかし、日本語には現代語の他に古語が存在する。
ご存知の通り、古語には純粋に「過去」を意味する助動詞が存在する。それが「き」や「けり」である。古語の助動詞「たり」が現代語では「た」に変形したこととは対照的に古語の助動詞「き」や「けり」は現代語では完全に姿を消してしまっている。現代語では純粋に過去を示す表現が消えている。「き」や「けり」が消えたから現代語では「た」が過去の意味を持つようになったのか、「た」が過去の意味を持つようになったから「き」や「けり」が不要になって消えたのかは知らないが、いずれにせよ、現代語では「た」が「完了」と「過去」という二つの意味を持つと考えられるようになった。前にも述べたとおり「完了」と「過去」とは似たように見えて本来は全く別の次元のものである。
以上のことを踏まえると、「古語の厳密な現代語訳は可能なのだろうか」という最初に示した疑問にたどり着く。そこでもし仮に古語を厳密に現代語へと訳すことが不可能もしくは非常に困難だとするならば、少し古語を使ってみようかと思うようになった。そしてそれを当サイトで試すこととする。
(古語)
「き」、「けり」→過去の意味
「つ」、「たり」など→完了の意味
(現代語)
「た」→過去の意味も完了の意味も
(当サイト)
「けり」→過去の意味
※「き」ではなく「けり」を使っている理由についてはこちら